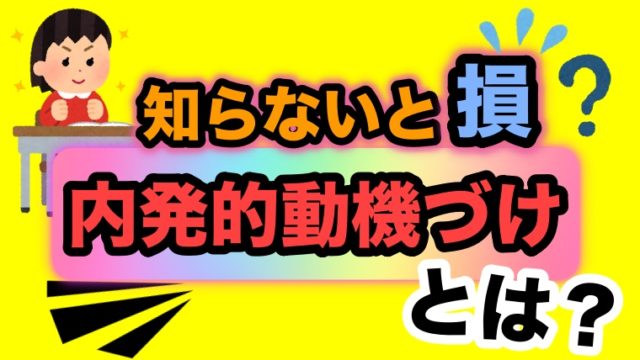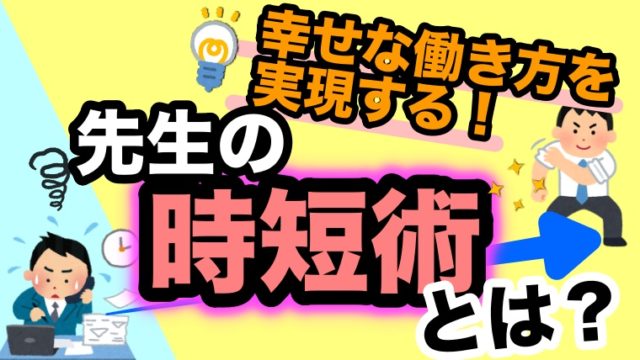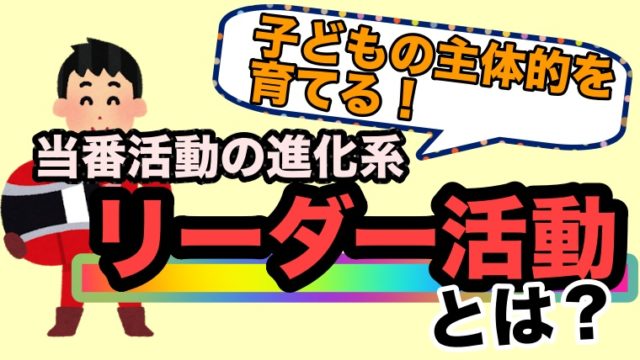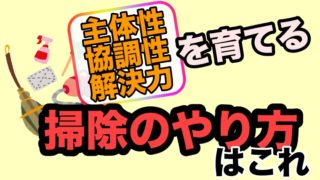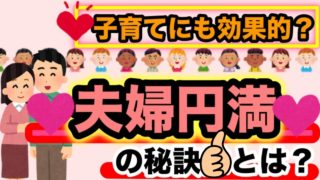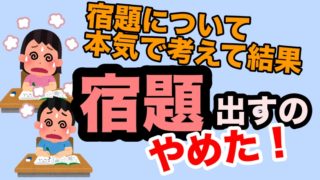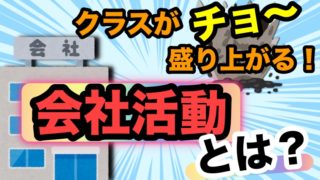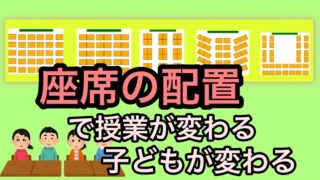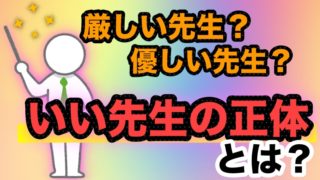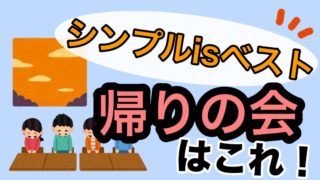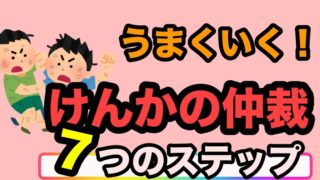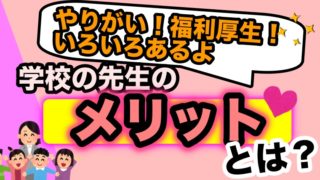どうもガクせんです。
以前に「男の子育て方」について解説しました。

ということで、今回は、女の子の育て方に悩んでいるあなたに「女の子の育て方」について解説していきます。
男の子の子育ての悩みの多くは「行動面」が多い一方、女の子の子育ての悩みは「精神面」や「関係性」に多いようです。
今回の記事を読めば、きっとそんな悩みも解消していけます。
まずは、相手(女の子)の特性を知り、効果的な接し方を学んでいきましょう。
- 女の子の特性を知ることができる。
- 女の子の子育てや学級経営上の悩みが減る。
- 女の子の育て方が分かり、子育てや学級経営に自信が生まれる。
ではまいりましょう!
目次
女の子の謎にせまる

まずは、「女の子の特性」を理解していきましょう。
そのためには、まず人類史において、女性がどんな役割を果たしてきたのか、どんな生活をしてきたのかを知ることがポイントになります。
そこを皮切りに、深堀りしていきたいと思います。
女の子には、コミュニティを大切にする生き物
人類史の99%をしめる狩猟採集時代において、女性は、男性が遠方まで狩りに出かけている間、木の実や根菜類などを採集し、コミュニティをつくって生活していました。
つまり、「コミュニティを大切にしたい」という本能が、現代を生きる女性のDNAにも深く刻まれているのです。
そのことを頭に入れて次にいきましょう。
話したい
コミュニティを形成していく上で、欠かすことができないのがコミュニケーションです。
そのため、女の人は言語の脳領域が、男性に比べ発達していることがわかっています。
また、男性は狩りを成功させるてめに会話をしていたため、会話に目的を求めます。
一方、女性はコミュニケーションのための会話が中心になるので、会話に共感を求めます。
そのため、共感してもらえることに大きな喜びを感じるのです。
貢献したい
男性にも「貢献したい」という気持ちはあるのですが、女と男とでは少し貢献に対する捉え方が違います。
男性の貢献感は「貢献することで自分の力や地位を誇示したい」という気持ちが強く、女性は「貢献することで、自分を必要としてもらいたい」という思いが強いと言われています。
なので、女性は
という言葉に喜びを感じます。
お世話をしたい
女性特有の能力と言えば「出産」です。
そのため、個人差はありますが、女性のDNAには「お世話をしたい」という本能が刻み込まれているのです。
ボクは現在、女の子、男の子の子育て中なのですが、その男女の違いにはいつも驚かされています。
娘は、もう2歳くらいからお人形を抱っこし可愛がっていましが、息子はその姉の人形を車に見立てて走らせていました。笑
精神年齢が高い
「お世話をみたい」という本能とも関係する部分ですが、一般的に女の子の精神年齢は同年代の男の子より高いと言われています。
実際に、ボクの教員経験、そして子育て経験を踏まえてみてもこれは間違いなさそうです。
この精神年齢の差に関しては、科学的な根拠は無く、「精神年齢が高い=落ち着いている」という社会的な認識が、男女の精神年齢の差を生み出しているみたいです。
理由としては
女性は出産育児をに担っていたため現実的、堅実的思考が強く、「落ち着いている」と認識される。
一方、男性は狩りに出かけるため、冒険心が強く多動傾向があるので「落ち着いていない」とみなされる。
これが「精神年齢の差」として認知されているのではないかと考えられています。
みんなと同じが好き
ある幼稚園で、女の子のグループと男の子のグループに分け、「ボールをどの高さまで投げられる?」という質問をしました。
その結果
男の子のグループでは、1人目が答えた高さより、2人目はより高く飛ばせたと答え、3人目は、2人目より高く飛ばせたと答えました。
一方、女の子のグループは1人目が答えた高さに、2人目、3人目も「同じ」と答えたのです。
この結果から
男の子は、自分が人より優れていることを好む
女の子は、みんなと同であることを好む
ということがわかります。
狩猟採集時代を考えれば、男性は、人よりも狩りの能力が高いことが評価され、女性はコミュニティを円滑に保つ能力が求められていたのでこのような差が生まれていったのでしょう。
つまり、女の子は男の子に比べ、みんなと「同じ」だと安心するという傾向があるということを覚えておいてください。
女の子の子育てのポイント

以上のような、女の子の特性を理解し、子育てに活かしていくことが大切です。
次に、具体的な子育てに役立つポイントを解説していきます。
ポイント①話しを聞き、共感しよう
とにかく、「話を聴く」「共感する」という行為は女の子の子育てにおいて基本中の基本になってきます。
特に男親や男の先生は話を聴くことが苦手な人が多いです。
といった傾向があります。
大切なのは
という「心から聴く」「共感する」という姿勢です。
女の子は、心から話を聞いてもらえたことに喜びを感じ、相手に信頼を寄せます。
ポイント②貢献できる場をつくろう
女の子は「貢献したい」「自分を必要として欲しい」という本能をもっているという話をしました。
そこで、家庭や学校において「貢献できる場」を用意してあげましょう。
- 家庭では、家事のお手伝い
- 学校では、当番活動
などが考えられます。
ボクの家では、娘は洗濯物をしまってくれたり、料理をしてくれたりと喜んでいろいろなことをやってくれます。
ポイントは
です。
学校では、当番活動ならぬ「リーダー活動」がオススメ!
詳しくはこちら↓
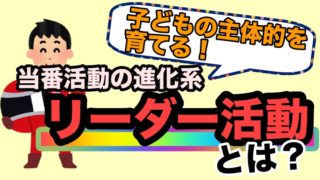
貢献できる場を提供し、やってくれたときには「あなたがいてくれて助かるよ」「あなたがいてくれてよかった」と感謝の言葉をかけてあげましょう。
きっと「私は必要とされているんだ」という気持ちを育ててあげることができ、良好な関係を築いていけます。
ポイント③お世話したい気持ちを満たしてあげよう
女の子の「お世話をしたい」という気持ちを満たしてあげることは、女の子の成長をいい方向へ促すことになります。
方法としては
アンダードッグ効果とは、弱い立場の人に対し、同情して応援したり、味方をするという心理的効果
3つに共通するところは、子ども自身が「自分がなんとかしてあげなきゃ」と思える環境をつくるということです。
ここで交流分析という心理学のパーソナリティ理論について簡単に説明させてください。
交流分析によると、子どもも含め人の中には以下の三つの自我があると提唱されています。
- 子どもの自我
- 大人の自我
- 親の自我
この3つの自我は入れ子構造になっており、子どもの自我が出ている時には、大人や親の自我は引っ込みます。
つまり、子どもの中の「親の自我」をうまく引き出してあげることが、女の子の「お世話をしたい」という欲求を叶え、健全な成長へと導いていけるということです。
もし、大人がずっと「○○しなさい」「お父さんがやってあげる」と<親の自我>で接し続ければ、子どもはずっと<子どもの自我>しか出すことができません。
なので、時には、「お父さん、これ苦手だから○○ちゃんお願い」と大人が<子どもの自我>を見せることも大切なのです。
先生も、子どもに「まったく先生ったら仕方ないなあ」「世話が焼けるなあ」と思わせることで子どもの<親の自我>を引き出すことができます。
お世話してくれた時には、「ありがとう」と感謝を伝えることで、貢献感につなげることもできますね。
ポイント④同じ物を持とう、好きなものを共有しよう
女の子は「みんなと同じが好き」という話をしましたが、この本能も子育てにおいて、学級経営において役立てることができます。
つまり「同じものを所有する」「好きなものを共有する」ということです。
例えば、同じキーホルダー、同じ柄のハンカチなど、同じものを所有しているだけで、女の子は仲間意識をもってくれるようになります。
学級経営で考えると、学級目標や学級キャラクターのステッカーなどをみんなに配るのも、仲間意識を育てるのに役立ちますね。
また、好きなものを共有するのもとても効果的です。
もし、子どもが「すみっコぐらし」が好き、「ジャニーズが好き」と言った場合には、その良さを理解し、一緒に楽しむことがオススメです。
まとめ
女の子の特性から、女の子の育て方のポイントまで解説してきましたがいかがだったでしょうか。
まとめると
- 女の子はコミュニティを円滑に保とうとする本能がある。そのため、会話、共感、貢献、お世話、同じ、ということに価値を見出す。
- 女の子の本能を効果的に引き出しながら子育てすることが大切。
ということでした。
相手や己を知ることで、幸せな子育てを実現していくことができます。
もちろん、個人差もありますので、実際に子どもたちと接しながら、その子の特性を十分に理解し、特性に合わせた子育てを生み出していっていければと思います。
今回の記事が少しでもお役に立てたら嬉しいです。
随時、学級経営や子育てに関するご相談はTwitterで受け付けています。
お気軽にDMください。(もちろん無料ですのでご安心を)
こんな人におすすめ
- 子どもとの関係づくりに悩んでいる
- 子どもの主体性を引き出せる力を身に付けたい
- 先生という仕事や子育てが辛い
※相談人数が多い場合は、ご対応に時間がかかる場合やお断りする場合がございますのでご了承ください。